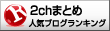アカエイのフライや地元産の野菜を挟んだ「エイバーガー」(鈴木渚斗さん提供)
大きいもので体長1メートル以上にもなり、網を破壊したり貝を食べてしまったりすることから、漁師たちに「厄介者」と呼ばれているアカエイを食材として活用する試みに、島根大大学院生らが取り組んでいる。ハンバーガーや軟骨のから揚げなどの新メニューを開発しているが、なかなか好評のようだ。
かつては煮こごりとして重宝
12月13日、松江市内の道の駅で開かれたアカエイを使ったメニューの試験販売。揚げたエイのヒレに、たくあん入りのタルタルソース、地元産のレタス、トマトを挟んだハンバーガーが登場したほか、メンチカツ、軟骨のから揚げが用意され、長蛇の列ができる人気ぶりだった。
食べた市内の20代公務員の男性は「食べる前は生臭くて硬いイメージがあったが、サクッとしていて身も柔らかかった」と満足そうに話した。
企画したのは島根大大学院2年生の福田聖(あきら)さん(25)。同級生で大学時代にアカエイを研究していた鈴木渚斗(かいと)さん(25)から「漁師が困っている」と聞いたのが商品開発のきっかけだった。
アカエイは海で生息するが、海水と淡水が混じる汽水湖でも生息できる。地元では宍道湖(松江市)と中海(島根、鳥取両県)で近年数を増やしており、漁師たちにとって「厄介者」になっている。大きいもので1メートル以上の大きさになり、刺し網に掛かって暴れて破壊したり、はえ縄を切ったりする。中海のアサリを食べるなどの食害も報告されている。
かつては鮮魚の乏しい山間部を中心に、ヒレを使ったゼリー状の「煮こごり」として重宝されたが、近年は食べられなくなった。市場でもほとんど値が付かないという。
松江城のお堀でも目撃
鈴木さんによると、宍道湖のモニタリング調査で平成22年に比べて28年に生息数が約10倍に増えたというデータがあるという。夏場には松江城の堀や側溝でも目撃されている。
増加の原因について、鈴木さんは「水温が上昇し、海に出なくても中海や宍道湖で越冬できる環境が整っているのではないか」と推測する。
汽水湖はもともと魚種が豊富で、天敵となるサメもいない。そのためアカエイにとって暮らしやすい環境になっているようだ。
続きはソースで
https://www.sankei.com/west/news/201225/wst2012250005-n1.html
引用元: https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/editorialplus/1608882854/
煮付けとか不通に旨いんだが
けど、毒針が怖いから、ほんとに釣りたくない。